|
建築基準法は、2級FP技能士試験の不動産の中では最重要項目です。2級FP技能士試験においては、学科試験、実技試験ともに出題が予想される箇所であり、特に、実技試験が個人資産運用設計である場合は、ここから、計算問題も出題されるものだと思っていてください。
では、建築基準法について説明していきましょう。まず、建築基準法の存在意義から考えてみます。
これは、火事になったときを想像すると理解しやすくなります。1件火事になったら周囲の家がみんな燃えちゃったとか道が狭くて消防車が近寄れないないとかこれでは怖くて家など建てられませんね。ですから、建物を建てるときはある程度の規制が必要となるのです。つまり、建築基準法の目的は、「建築物の安全確保・良好な建築環境の確保等」のためということです。ここは、試験にはでませんが覚えておくと後の理解が楽になります。
では、具体的にどんな規制について説明します。まずは「接道義務」についてです。
接道義務は、法律的な表現で説明すれば、

「都市計画区域内・準都市計画区域内の建築物の敷地は原則として建築基準法上の道路(自動車専用道路のぞく)に2m以上接していなければならない。」
となります。文章でみると難しいので図で見てみましょう。
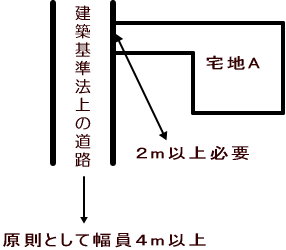
宅地Aのような土地の場合は、道路と接している部分が原則として2m以上必要だということです。「建築基準法上の道路」とは、原則として幅員4m以上(一部6m以上)の道路で法によって認められたもの等を言います。図で見ると簡単な話ですね。2級FP技能士試験対策としては、「原則として建築基準法上の道路」「2m以上接して」「幅員4m以上」の部分をまず押さえておきましょう。
そしてもうひとつ!建築基準法上の道路の代表的な例外もあわせて覚えておきましょう。

名前を「2項道路」といいます。
この定義は、
「建築基準法が適用された際に既に建築物が立ち並んでおり、特定行政庁から指定をうけた道路に関しては幅員が4m未満であっても道路と認められる。」
つまり、幅員4m未満であっても「建築基準法上の道路」と認められている道路があるということです。よくある出題パターンは、「必ず4m以上の・・・」です。必ずではありませんから、このような記述は間違いですね。
ところで、上記記述に「既に建築物がたち並んでおり・・・」とありますね。ま、建ってるものは仕方ありませんが、接道義務を満たさないまま放置するのもまずいですよね?火事になったときを想定してみてください。
良くないですね。
そこで、次に建物を建てるときは、「道幅4メートルを確保した上で建ててください」という規定があります。これをセットバックといいます。下の図をみてください。
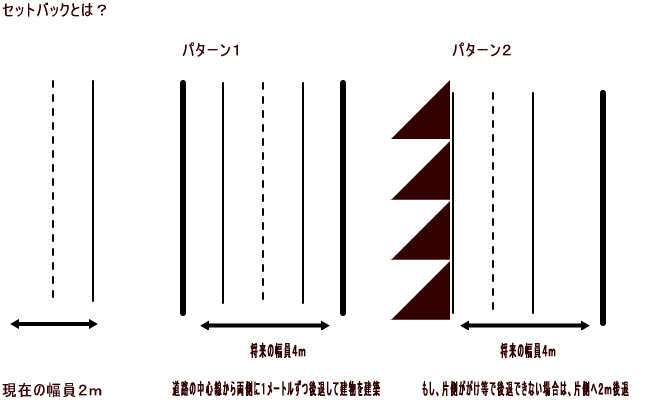
図からわかるとおり、セットバックとは、現在は、道路の幅員は、基準を満たしていないとしても、将来的には、建築物は、図中の太い実線の外にしか建てられない様に規定をして将来の道路の幅員を確保しているということです。
このセットバック部分については建物が建てられない訳ですから、建ぺい率や容積率の計算に含まれないことになっています。建ぺい率と容積率については次回以降に説明します。
  


|
本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。
Copyright(c)2007年−2017年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights
Reserved
|
| ![]()
